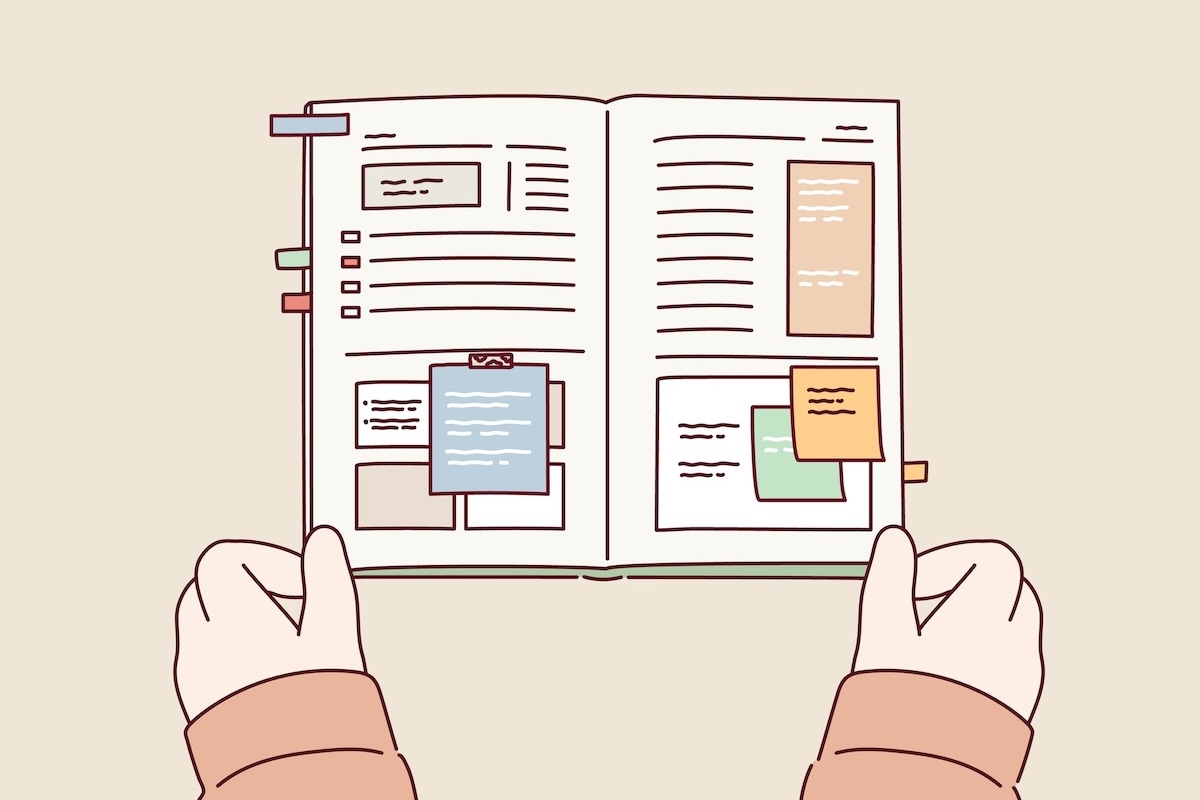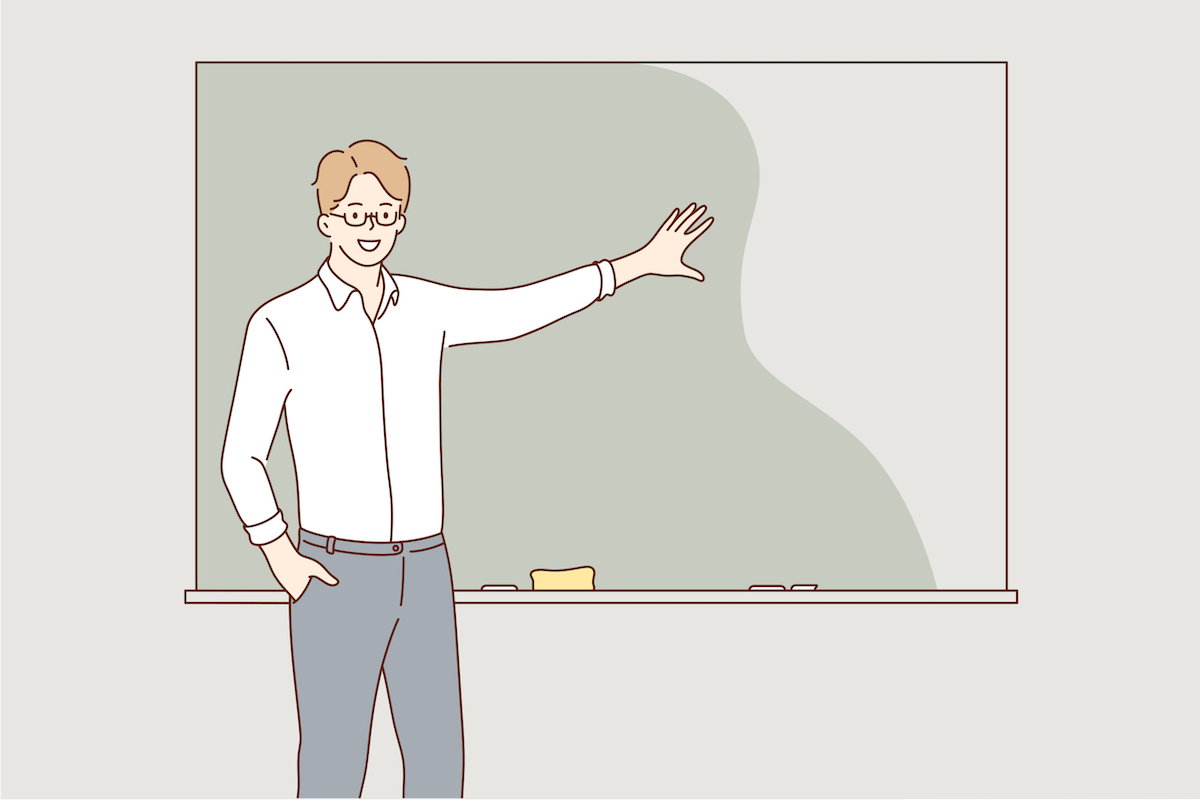こんにちは。ひろポンプです!
「ビジネス上で役立つ資格をとりたい!」と考えたときに、宅建(宅地建物取引士)の資格に興味を持つ人はかなり多いのではないでしょうか?
不動産業界で大きな活躍が期待できる宅建は、日本でも有数の人気を誇る国家資格です。
- 宅建士ってそもそもどんな仕事なのか教えてほしい、、
- 宅建士にしかできない独占業務の内容を知りたい。。
- 宅建の資格は不動産業界でちゃんと活かせるの??
宅建士を目指すにあたって、上記のような疑問や不安を感じてしまう人はきっと少なくないはずです。
今回は、【宅建士ができること+活かし方】3つの独占業務とはどんな仕事?というテーマで話を進めていきます。
賃貸仲介・賃貸管理・売買仲介など約5年の実務経験あり
宅地建物取引士・FP2級・簿記2級を保有しています
フリーランス宅建士として『ひろポンプ不動産』を運営中
宅建に合格した後、宅建士になると、宅建士にしかできない業務(独占業務)が与えられます。実務経験期間の長短は関係なくいきなり独占業務を行うことができます。
実際に私も新卒で正社員として不動産会社に入社する前に、インターン生として宅建士の業務をやらせていただく機会がありました。
年齢や経験に左右されない宅建士は、やりがいがある素晴らしい仕事です。記事の後半では私の体験談を交えながら、宅建士の実情や活かし方についても深掘りしていきます。
ぜひ最後までご覧ください。
YouTube動画でも解説してます!
宅建士のみができる3つの独占業務とはどんな仕事?

さっそく、宅建士のみができる独占業務とはどんな仕事かを解説していきます。
独占業務は3種類あって、下記の通りにまとめてみました。
- 重要事項説明書(35条書面)への記名
- 重要事項説明書(35条書面)の説明
- 契約書(37条書面)への記名
「重要事項説明書と契約書って何が違うの?」と疑問に思いますよね。私も不動産会社に入ってからそれぞれの違いを完璧に理解できるまで約1年間かかりました、、笑
「私はちゃんと理解しているわよ!」という不動産業界で働く人にも復習も兼ねて、この後の説明を見てもらいたいです。
なぜかというと、誰もが知る大手の不動産会社でも間違って認識しているケースが度々発生しているから……それだけ難しく複雑な業務なので、きちんと学んでいきましょう。
宅建士には独占業務の他に、『不動産業を営む場合、ひとつの事務所につき5人に1人以上は宅地建物取引士を設置しなければならない』という設置義務が定められています。
不動産業界において、宅建士はなくてならない存在です。取って損はしない資格だと思いますよ!
重要事項説明書(35条書面)への記名
まず1つ目は、重要事項説明書(35条書面)への記名について解説します。(重要事項説明書は、略して“重説”とも言います)
重要事項説明書とは、売買もしくは賃貸契約締結の意思決定にあたって重要な事項が記載されている書面です。
もう少し噛み砕いてご説明すると、契約を行う前に買主もしくは借主が「この物件の価格or賃料は?」「この物件の周辺は何か危険な区域なの?」「将来自分の意思とは関係なく手放す可能性がある権利が付いている?」と様々なポイントを理解する書類です。
もっと簡単に一言でいうと、“契約しようとしている物件の詳細が書かれた説明書”というイメージでOKだと思います。
この重要事項説明書に記名を行うのが、宅建士に与えられた独占業務の1つです。
重要事項説明書が35条書面と呼ばれるのは、不動産の法律である“宅地建物取引業法”の第35条に重要事項説明書のことが記載されているためです。
重要事項説明書(35条書面)の説明
続いて2つ目は、重要事項説明書(35条書面)の説明の解説です。
重要事項説明書の内容を説明するのは、宅建士にしかできない仕事です。
重要事項説明書に記載されている文言を読んだだけでは、ごく普通の人では理解できないのが当然です。
たとえば賃貸物件で『抵当権』と呼ばれるものが物件に登記されていた場合、6ヵ月間以内に物件を退去しなければならないリスクがあるのですが、それを知らずに契約してしまうと後々トラブルになりかねません、、
また極端な例かもしれませんが、ペットを飼おうとしている人に対して、重説にペット禁止の記載があったとしたら契約前に気づかせることも可能です。
不動産取引のプロフェッショナルである宅建士の仕事の中で、安心して契約を結んでもらうことが、3つの独占業務の中でも最も重要かもしれません。
契約書(37条書面)への記名
最後の3つ目は、契約書(37条書面)への記名を解説していきます。
先ほどの重要事項説明書が“契約しようとしている物件の詳細が書かれた説明書”と表現しましたが、契約書(37条書面)を一言でいうと、“売主と買主or貸主と借主の約束事が書かれた書面”です。
この契約書(37条書面)にお互い合意して、契約書の締結を交わした際に初めて契約成立となります。※民法では諾成契約が採用されていますが、実務的にはサインする前であればキャンセルできることが一般的なので、ここでは考えないことにします
この契約書に記名を行うのも、宅健士のみができる立派な独占業務です。
ちなみに契約書には説明責任はなく、交付のみで問題ないと法律で決まってはいますが、実際のケースでは契約者に契約書の内容もきちんと説明するのが通例です。
お客様の立場になって、「重説は説明したから、契約書は勝手に読んでください」と突っぱねられたら、逆に困ってしまいますよね(笑)
重説と契約書のそれぞれの内容に相違がないかも確認しつつ、宅建士として責任をもって自分の名前の記入と自分の名前の印鑑で捺印をしていきましょう。
契約書が37条書面と呼ばれるのは、重要事項説明書が35条書面と言われていると同じ理由で宅建業法の第37条に契約書について記載されているからです。
不動産業界における宅建士の実情+活かし方

ここまで、宅建士のみができる3つの独占業務とはどんな仕事なのかを詳しくご紹介してきました。
「全然知らなかった、、宅建士の仕事って楽しそう!」と少しでも思っていただけたら、この記事を書いた意味があるかなと嬉しい気持ちになります。
ここからは、私が不動産会社で宅建士として丸5年以上働いた体験談を含めて、不動産業界における宅建士の実情と活かし方を深掘りして話していきます。
少しでも宅建士の仕事について興味が持っている人は、ぜひ参考にしてみてください。
意外と法律を守っていない業者がたくさんいます…
まずは意外な真実かもしれませんが、法律を守っていない業者がいっぱいいます、、
“守っていない”というよりは、“知らない”という日本語で表現した方が正しいかもしれませんね。
具体例を挙げると、宅建士の重要事項説明書の記名は、取引態様が『貸主』の場合には不要で、それ以外の『媒介』や『代理』は必ず必要となります。
ただなぜか大手の不動産会社の中には、取引態様が『代理』なのにも関わらず、宅建士の記名がないケースが頻発して起きているのが実情です、、
もちろんそのまま契約を締結してしまうと宅建業法違反で罰せられてしまう可能性があるので、上記の旨を説明して重説の再発行を依頼します。
ちなみに今説明した内容はかなり複雑な内容のため、全く理解しようとしないでOKです!(私もきちんと理解できたと自信を持って言えるようになるまでに約3年かかりました。。)
実際に私は「これってどういうことだ?」と分からない事例があるたびに、都庁の不動産窓口に何度も連絡して相談をしながら覚えていきました。(多分50回以上電話したので迷惑なヤツですね、、汗)
お客様の大切な契約のために、宅建士になっても日々勉強していきましょう!
宅建士の資格手当で年収60万円UPの可能性アリ
「宅建に合格すると年収が上がる?」という噂を聞いたことがある人もきっと多いはずですよね。
実情として宅建士になる→給与UPは真実と言っていいでしょう!
資格手当として毎月5万の支給がある不動産会社も数多いので、年収で考えると60万円UPが期待できます。
また年収UPだけではなく、昇進や昇給も早いタイミングで見込めるはずです。
たたし宅建士の資格手当・優遇は会社ごとによって異なるので、これから就職を考えている人は面接時に、すでに不動産会社で働いてる人は社内規定を確認するのをおすすめします。
ちなみに他にも宅建を取得すると得られるメリットはいくつか存在します。別の記事にまとめているので、気になる方は下記のリンクからご覧ください。
私が新卒で入社した会社では、残念ながら資格手当はありませんでした、、泣
ただ入社時から宅建士だった分、昇給や昇進は周りに比べてかなり早かったのではないかと感じています。
不動産業界で働くなら宅建合格は最低ライン
今まで宅建士ができることや実情などを解説していきましたが、最後にみなさんにお伝えしたいことがあります。
それはズバリ、不動産業界で働くなら宅建合格は達成するべき最低ラインです。
もちろん宅建の資格を持っていなくても不動産業界へ就職・転職は可能ですし、そのまま不動産業界で働いている人も大勢います。
ただ“不動産業界で宅建の資格を持っていない”ことは、“コース料理の高級店のシェフが100均の包丁を使っている”もしくは“眼鏡屋の店員さんがコンタクトをつけて働いている”と同じくらい、いやそれ以下のレベルでお客様へ良いサービスをお届けできないと考えます。
少し厳しい意見かもしれませんが、私が不動産会社に勤めていない素人だとして、『宅建の資格を持っていないアマチュア』と『宅建士のプロ』であれば、自分が汗水流して得たお金を不動産取引で大金を支払うことを任せるなら、間違いなく私は『宅建士のプロ』を選びます。
きっと私と同じ意見な人が大多数なはずですよね?
宅建は合格率が約15%で難関の資格と言われていますが、基礎をしっかり固めれば誰でも合格を十分に狙える資格です。
不動産業界で働くことを検討しているのであれば、宅建士として立派に独占業務を行うためにも、まずは合格を目指して勉強をスタートさせてみましょう。
以上です。
最後は少し冷たく聞こえてしまったかもしれませんが、それだけ宅建士は責任のある仕事でもあり、やりがいのある仕事でもあります。
また法律の考え方やお客様のニーズを満たす解決法を模索していく業務でもあるので、ビジネス全般で役立つことも多いですよ。
「宅建いいかも!勉強してみようかな?」と思った人はすぐ行動に移してみましょう。きっとあなたなら合格できるはずですよ!!
上記の記事で独学での勉強法・おすすめの通信講座をまとめているので、気になる方はぜひチェックしてみてください。
それではまたどこかでお会いしましょう(#^.^#)